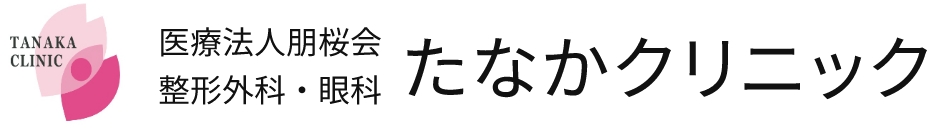整形外科とは

身体運動に関係する部位(神経、骨、筋肉、関節、腱など)を総称して運動器と言い、これらで発生したケガや病気について、診察・検査・治療を行っていくのが整形外科です。
整形外科は、年齢制限はなく、生まれたばかりの新生児からご年配の方まで幅広い世代を対象にしています。小さなお子さまであれば、先天的な運動器の疾患である先天性股関節脱臼をはじめ、幼少時のX脚やO脚、ペルテス病などについてもご相談ください。また学校での運動器検診において、何らかの異常(脊柱側弯症、腰椎分離症、オスグッド・シュラッター病 等)を指摘されたという場合も一度ご受診ください。
また、日常生活でよく起きやすいとされる、肩こり、腰痛に悩まされている、ぎっくり腰になった、膝の関節が痛むといった場合はもちろん、突き指、打撲、捻挫、骨折などのケガにつきましてもお気軽にご受診ください。このほか交通事故によるケガもご相談ください。
なお医師による診察の結果、CTやMRI等による詳細な検査が必要、入院加療を要するという場合は、当院の提携先医療機関である総合病院などを紹介いたします。
当診療科で対応する主な症状(例)
- 首や肩にこりがみられる
- 腕を挙げることができない
- 手や肘、腕、あるいは首や肩に痛みがある
- 背中、腰、股関節、膝、脚などが痛む
- 手や足にしびれを感じる、あるいは感覚が鈍くなっている
- 力を手足に入れることができない
- 手指がこわばっている、もしくは脹れている
- 指を伸ばす際に引っ掛かりを感じる
- 突き指をしてしまった
- 捻挫、骨折、打撲、脱臼などのケガをした など
部位(症状)別でみる整形外科領域の主な疾患
| よくみられる症状 | 考えられる主な疾患 |
|---|---|
| 首の痛み | 頚椎症、頚椎症性神経根症、頚椎椎間板ヘルニア等 |
| 肩のこり、痛み | 頚肩腕症候群、五十(四十)肩(肩関節周囲炎)、肩腱板損傷等 |
| 手のしびれ | 頚椎椎間板ヘルニア、手根管症候群等 |
| 肘の痛み | 上腕骨外側(内側)上顆炎(テニス肘、野球肘など)、肘内障、肘部管症候群、変形性肘関節症、離断性骨軟骨炎等 |
| 手・手首の痛み | 手根管症候群、関節リウマチ、腱鞘炎、変形性手関節症等 |
| 手の指の痛み | ばね指、突き指、デュピュイトラン拘縮、ヘバーデン結節等 |
| 腰の痛み | 腰痛、ぎっくり腰、腰椎椎間板ヘルニア、変形性腰椎症、腰部脊柱管狭窄症、胸・腰椎圧迫骨折、腰椎分離・すべり症、坐骨神経痛、骨粗鬆症等 |
| ももの付け根の痛み | 変形性股関節症、単純性股関節炎等 |
| 足のしびれ | 腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、慢性閉塞性動脈硬化症(ASO) 等 |
| 膝の痛み | 変形性膝関節症、靭帯損傷、半月板損傷、オスグッド病(小児)、関節水腫、関節ねずみ(関節内遊離体)等 |
| すねの痛み | シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)等 |
| 足の痛み | 足底筋膜炎、扁平足、アキレス腱断裂等 |
| 足指の痛み | 外反母趾、巻き爪(陥入爪)、痛風、関節リウマチ等 |
腰痛
腰が痛む病気のことを総称して腰痛症と言います。その中でも原因が特定できる腰痛が特異的腰痛で、原因が特定できない腰痛を非特異的腰痛と言います。特異的腰痛は、原因がはっきりしており、外傷による骨折、神経が圧迫される、脊髄の病気等によって引き起こされます。腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、骨粗鬆症、化膿性脊椎炎などの患者様が含まれます。
ただ原因が特定できない腰痛を訴える非特異的腰痛の患者様が多く、さらに急性腰痛と慢性腰痛(3ヵ月以上続く腰痛)に分けられます。
急性腰痛は発症から4週間以内の腰痛を言います。主にぎっくり腰(腰椎捻挫)のケースが多く、重いものを持ち上げる、腰を捻るなどで、腰の筋肉に肉離れが起きる、腰椎の関節部分にずれが生じるなどして発症すると言われています。症状としては、腰を動かそうとすると痛みが出て、安静にしていると軽減しますが、この状態が長く続けば筋力は低下していきますので、痛みが強く出なければ動かしていくことも大切です。
慢性腰痛のケースでは、腰に鈍く重い痛みを感じるようになります。原因が特定できないとされていますが、姿勢の悪い状態を長時間続けていることや運動不足、肥満、心理的要因(ストレス、不安、うつ 等)などが考えられます。
治療に関してですが、急性で痛みが強ければ、消炎鎮痛薬(NSAIDs)やブロック注射等の薬物療法やコルセットによる装具療法などを行います。痛みが軽減すれば、リハビリテーションを行い、生活習慣(姿勢が悪い、運動不足 等)を改善していきます。また慢性腰痛で、うつやストレスなど精神面が原因とされる場合は、抗うつ薬や抗てんかん薬による薬物療法やリハビリテーションを行います。
腰椎椎間板ヘルニア
背骨と背骨の間には椎間板という軟骨があります。腰椎椎間板ヘルニアでは、この腰椎部分にある椎間板が何らかの原因によって変性し、これが後方に突出することで神経根を圧迫し、症状が出現します。
椎間板が変性する主な原因は、加齢が大半とされていますが、重い荷物を持つなどの労働を繰り返す、スポーツによる腰への多大な負荷などによって引き起こされます。診断には、X線検査やMRIなどを撮影します。
治療としてはまず保存療法として薬物療法(NSAIDs、筋弛緩薬 等)やブロック注射(硬膜外、神経根)で痛みを緩和する、コルセットによる装具療法などをしていきます。なお保存療法では症状が改善せず足の運動障害などがみられる場合は、椎間板を摘出する手術療法が行われる場合があります。
肩こり
首から肩にかけての筋肉などに張り、凝り、痛みなどの症状がみられるほか、頭痛や吐き気などが現れることもあります。
発症の原因は2つあるとされています。ひとつは、病気など原因が特定できる症候性肩こりです。整形外科領域の疾患の一症状であれば、頚椎症性神経根症、椎間板ヘルニア、肩関節周囲炎(四十肩、五十肩)、肩腱板損傷などが考えられます。また循環器疾患(狭心症、心筋梗塞、高血圧 等)や目の異常(視力障碍、眼精疲労 等)、心の病気(うつ病 等)ということもあります。これらの場合は原因疾患に対する治療が必要となります。
もうひとつのタイプは、原因がはっきりわからないとされる本態性肩こりです。この場合、精神的なストレス、VDT作業(PC画面を見続けながらの長時間のデスクワーク 等)、姿勢が悪い、運動不足などが挙げられます。
治療に関してですが、肩こりの原因が特定しているのであれば、原因に対する治療を行います。また原因が特定できない場合は、長時間同じ姿勢になりやすい方はこまめに休憩をとる、合間に軽く首や肩を回すようにします。また運動不足の方は適度に運動をするようにしてください。さらに血行を促進させるために入浴などで肩を温める、ストレスを溜めない環境を整えるなどの予防対策に努めてください。それでも痛み等の症状が改善しないという場合は、一度当院をご受診ください。
五十肩
肩関節に痛みや可動域に制限がみられている状態で、40~60代の患者様が多いことから五十肩あるいは四十肩と一般的には呼ばれています。大半は左右の肩のどちらかにのみ症状が現れます。
この場合、主に老化によって肩関節の周囲(筋肉、関節包)に炎症が起きることから肩関節周囲炎とも呼ばれます。炎症によってこれら組織が硬くなるなどして、痛みや肩の動かしにくさなどの症状がみられますが、人によっては夜中に痛みが強くなって眠れなくなることもあります。痛みは何の前触れもなく起きるとされ、症状のピークは数週間程度とも言われますが、長く痛みが残る場合は1年程度続くこともあります。
自然に治癒することもありますが、痛みの症状を強く訴えている患者様には、消炎鎮痛薬(NSAIDs)による内服、患部に貼る湿布等を使用していきます。それでも痛みが改善しないという場合は、関節注射を行うなどして痛みを軽減していきます。また肩を安静にしたままにして動かさなければ、肩関節の可動域が制限されていきます。したがって状態に応じて肩関節を動かすなどのリハビリテーションが必要になります。
捻挫
捻挫とは骨を除いた靱帯を含む関節包や筋肉が炎症を起こしている状態です。靭帯の部分損傷が起こっている場合もあります。関節が本来であれば曲がることがない方向に曲がった、あるいは動くなどしたことなどによって発症します。主な症状は関節の痛みや腫れなどです。重症ではないからと放置を続け、関節内で傷を蓄積させるようなことがあれば、変形性関節症のような状態に陥ることもあります。
受傷時に骨折やケガの状態(靱帯損傷の程度)を調べるためにX線撮影を行うこともあります。治療については、患部の固定と安静が必要です。その後、硬くなってしまった靱帯や筋肉を軟らかくしていくリハビリテーションをしていきます。なお治療時にしっかり固定をしていかないと靱帯は伸びたままとなってしまい、関節は緩みがちになって、捻挫をしやすい体質になることもあるので要注意です。
変形性膝関節症
加齢をはじめ、膝関節の酷使や外傷などによって膝関節の軟骨がすり減る、あるいは変性することで膝関節に痛みや可動域の制限、長く歩くことができないという状態を変形性膝関節症と言います。加齢や肥満などはっきり原因が特定できない一次性変形性膝関節症と、関節リウマチや膝に外傷を負うなど特定できる原因がある二次性変形性膝関節症に分けられます。なかでも一次性の患者様が多く、中高年女性が大半です。
発症初期は動き始めにおいて膝に痛みを感じるようになりますが、動いているうちに痛みはそれほど気にならなくなります。次第に症状が進行していくと、階段の昇降や正座をすることが難しくなるほか安静時でも膝に痛みがみられるようになります。
治療をする場合、まずこれ以上膝関節に負担をかけないようにします。具体的には、肥満の方であれば減量します。また関節の周囲に筋力をつけるトレーニングをする、サポーターや足底板による装具療法も行います。痛みが強ければ、痛み止めの薬(NSAIDs 等)の内服や関節内注射を行います。
なお上記の保存療法では、痛みなどが改善せず、日常生活に影響が出ているというのであれば手術療法(骨切り術、人工膝関節置換術 等)が選択されることになります。